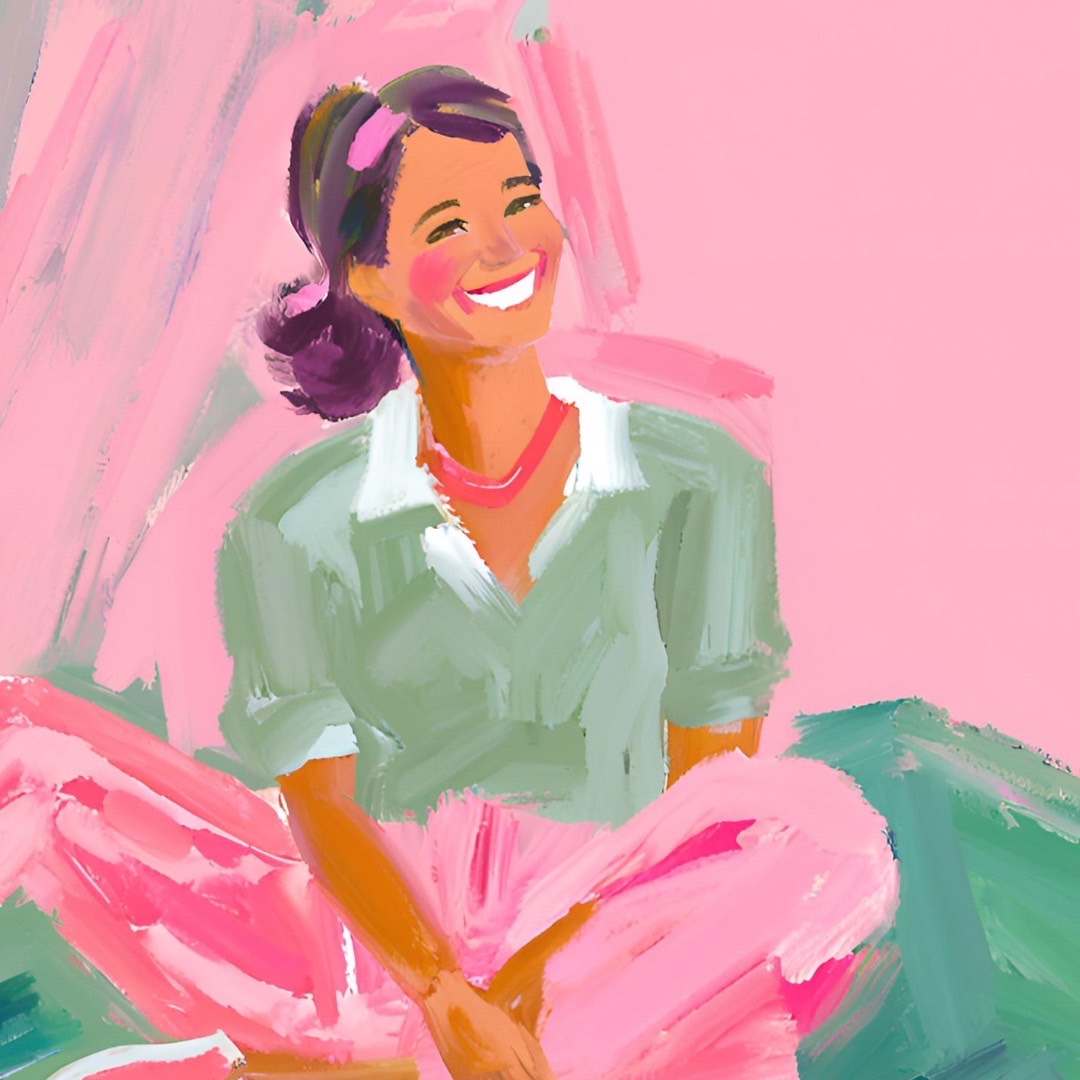ZENPE副代表 関口 桃子
副代表 関口 桃子 profile 東京都出身。 幼少期の入院がきっかけで出会った担当看護師に憧れ、進行・変動する難聴を持ちつつも看護師となる。難聴看護は、自身の経験を基に「どう対応するのがベストなのか」を考えながらケアすることを心掛け、「私にしか出来ない・なれない看護師とは何か?」を日々模索中。 新生児スクリーニング:パスと診断。 3歳:呼びかけの反応の悪さ・めまい発作で倒れ、耳鼻科受診するも病名はっきりせず。 5歳:右耳に真珠腫が発覚し手術する。右耳より左耳の聞こえが良かったため、左耳を頼りに幼稚園では裸耳で過ごす。手術入院で出会った担当看護師がきっかけで「将来の夢は看護師」と志すようになる。 市立の小学校へ入学(普通級) 低学年:担任より「ことばと聞こえの教室」を紹介され、放課後に他校で聴力検査と言葉の聞き取りの練習を行う。同時期に耳掛けの補聴器を紹介され左耳に片耳装用となる。回転性めまいや聴力のスケールアウトが頻回に起こり、ステロイド三昧でムーンフェイスであった。 市立の中学校へ入学(普通級) ベビークラスから水泳を習っており、水泳部に入部。水の中では不思議と声が聞こえた。高校受験のための内申、欠席日数も加味されるため発作が出ないかドキドキな日々を過ごす。高校入学前:紹介状を持たされ大学病院にて、ペンドレッド症候群と診断される。 隣県の私立高校へ入学(普通級) 高1:入学早々、授業中にめまいと聴力スケールアウトになる。様々な治療を試すも3ヶ月近くスケールアウト状態で退学の危機になるが、その後徐々に聴力回復し退学は免れる。定期試験で上位に入る事に重きを置き、大学受験は指定校推薦を獲得。念願の看護大学へ合格する。 都内看護大学(4年制)へ入学 電子聴診器を用いて実習を重ね、聴力ハンデを持った状態での臨床を見据えた対策を教員ととる。ストレートで進級し、看護師国家試験に合格する。 就職~現在入職と同時に、慶応大学病院主催の治験にも参加する。終末期ケアに携わりたく、急性期~終末期の消化器外科を主とする混合病棟に配属される。現場では想像以上に難聴であることが障害となる場面が多くあったが、周囲の助けや自身の経験の積み重ねで少しずつ対策を取りながら仕事を行えるようになる。産休育休を経て、現在は訪問看護師をしている。育児・仕事をしながら、在宅看護指導士・終末期ケア専門士の資格を取得。「私にしか出来ない・なれない看護師」になるべく奮闘中。 message 目が悪いと眼鏡をかけるのが当たり前という認識と同じくらい、耳が聞こえにくいと補聴器や人工内耳をしているのが当たり前な世界になってほしい。「遺伝疾患」は身体面のみならず自身や親・兄弟の心理面の影響が大きく、見た目で分からない症状が多く社会生活で「生きにくさ」が生じるかもしれない。それをどう工夫・対策をとって乗り越えてきたのか、同じような境遇の人・それを取り巻く周囲の人に一人でも多く知ってもらいたい!そして医療者として、少しでも生活がしやすくなるような試みを。活動を通して提供出来たらと思っております。
ZENPE理事 深沢 元樹
理事 深沢 元樹 profile 1975年、群馬県生まれ。姉が二人いる。三人姉弟の末っ子。 幼少時、幼稚園の先生より一つ上の姉と共に聞こえに問題があるのではと指摘を受け、検査したところ「感音難聴」と診断された。原因としては「元々聴神経が弱い性質で、頭を打ったのが原因」と。聴力は両耳共に50dB程度。 片耳だけ補聴器装用で問題ないとして地元の小学校普通学級に進学。 小学時、人と違うことをするのが嫌だった模様で、学校に補聴器を持って行ったもののほとんど装着せずポケットに入れていたと記憶。高学年になるにつれて渋々使い始めていたように思う。 中学校、高校と全く普通の青春時代を謳歌。その頃の聴力はありがたいことに安定しており、聴力が下がって行くなんて夢にも思っていなかった。医療機関にお世話になることもなく、ただ補聴器が壊れたら補聴器やさんで聴力検査を受けて新調してもらう、といった感じだった。だが実際にはジリジリと聴力は下がっていた模様で、恐らく60dBから70dB程度へと下がっていた。 その後、都内の専門学校に通いプロダクトデザインを学ぶ。デザインの基礎をみっちり学び、卒業コンクールで最優秀賞を受賞。 1995年、都会から離れたくて仕方がなく、恩師の紹介で地元の金型屋へ就職。当時出始めた3DCADシステムに早くから触れる機会を得てOSの基礎を学び、同時にホームページ製作に興味を持つようになる。ISDNとか、インターネット通信とか、ニフティとか、ポケベルとか、そんな時代である。そして、そのまま難聴とはほとんど向き合わずに普通の社会人として人生を謳歌し始める。 1998年、同僚にろう者が入社してくる。手話に興味を持ち、手話サークルに通い始める。どっぷり手話世界にハマる。 2000年頃、手話サークルのろう者と難聴者が和太鼓サークルを結成しており、誘われることでどっぷり和太鼓にハマる。 2003年、同じ難聴の姉が出産を機にスケールアウト。そのまま総合病院で検査したところ、難聴の原因が判明。ペンドレッド症候群による前庭水管拡大症、とのこと。姉から連絡があり、弟のお前もそうだから検査しろと言われる。が、とりあえず検査保留。 2010年、やっと自身の難聴と向き合い始める。サイト「50dBの世界」をオープン。ただ、当時おそらく70dB程度まで聴力が下がっていた模様だが本人自覚なし。 2012年、私自身の結婚を機に遺伝が気がかりとなり長野の信州大学で検査を受けたところ、やはり姉と同様にペンドレッド症候群との診断を受ける。遺伝についてはメンデルの法則の通りだがまあ心配ないと言われる。 そこから数日後、晩酌時に硬いあたりめを噛んでいたところ、奥歯がカキーンと噛み合った瞬間、突如右耳スケールアウト、左耳も悪化。一週間ステロイド点滴を受ける。ムーンフェイスの最中に結婚。その後少々回復し両耳とも85db程度に。 2014年、佐村河内事件発生。聴力50dBのキーワードで「50dBの世界」への訪問者急増。佐村河内事件を扱ったドキュメント漫画「淋しいのはアンタだけじゃない」の作者、吉本浩二氏より取材を受ける。仮名でその漫画に登場する。 2015年、息子誕生。 2018年、慶應義塾大学にて遺伝性難聴の研究をされていた藤岡先生の診察を受け始める。 2023年、藤岡先生より患者家族会が立ち上がっていることを知らされる。 同年、息子の誕生以降まったく更新できていない「50dBの世界」を閉鎖。 2024年、ZENPEに参加。 message 当時の母の日記が残っている。 その日記は古い戸棚の奥にしまってあり、だいぶ大人になってから発見したものだ。同じ難聴を抱えている姉と共に読んだ。それは涙なしに読めたもんじゃなく、嗚咽しながら読んだ。幼い二人の子が、ある日突然「感音難聴」と診断されてしまったのだ。当時30そこそこの若い女性であった母の憔悴がそのまま伝わってくるような、そんな内容だった。線路に飛び降りたいとか、死とか、その様なワードが最初に見られた。だがやがて、ことばの教室に通うことで私の発音が上達していくことを素直に喜ぶ内容になり、発音が不明瞭な箇所を毎日メモするなど、私と姉の成長記録へとそれは変貌していった。 2025年現在、80歳になった母はまだまだ元気で鎌倉彫のとある流派の師範代となり、活躍している。 鎌倉彫は、私が小学生だった頃に参加したワークショップがきっかけで始めたのだとか。学校から帰宅すると、居間の隅っこに置かれた座卓の上で彫刻刀を握りしめて作品と向き合っている母の背中を目にするのが常だった。そんな母の横でゴロゴロと寝転がり色々学校の話をしていたのを覚えている。 日記を発見した時、その内容について母に尋ねたことがある。母は普通の母だったし、鎌倉彫に家事に一所懸命でバラエティ番組でよく笑う普通の昭和の主婦に見えた。日記の内容に違和感を感じたのだ。「今となってはどうしてそんなに悩んでいたのか分からない」と母は答えてくれた。 私の父は自然をこよなく愛する男である。幼少の頃から山や川に連れて行かれ、河原でバーベキューして釣りをして森林浴をしてと、そんな贅沢な休日を過ごしていた。ファミコンの登場など夢にも思わなかった時代の話だ。父はまるで絵に描いたようなthe昭和の父といった感じで、高度経済成長期を支えたサラリーマンよろしくバリバリ働き、社交と称した飲み会に付き合い、家事と育児をほとんど母に任せていたように思う。だが、週末は釣りにキャッチボールにと外に連れて行かれ、男たるものはどうあるべきか、昭和の気概を叩き込まれたように思う。今となっては父の生き方は随分と楽だなと思うが、当時は家事と育児の大変さがそれほど周知されていなかった時代だった。 母と同じく80代となった今でも、父は愛車で日本のあちこちへと旅立ち、川や海で魚を釣っては車中泊、そして観光して帰ってきたりする。母を連れていったり、場合によっては一人で行くこともある。 今思い返せば、父は私の障がいについてほとんど気に留めておらず、普通の男児として扱っていたように思う。ひょっとして私が難聴だということをまだ知らないのかと、そんな愚にもつかぬ発想すら浮かぶ。 父のその様な接し方は、私自身が一人の普通の人間であると感じ成長するのに十分なほど効果があったと思う。 事実、難聴を抱える人生であったが、客観的に自分自身をどう見ても、普通の男の普通の人生だと感じている。 でもそれだけに、母の日記はショックだった。 こんな普通の家族で普通の両親、普通の子なのに、当時これだけの負の感情が沸き起こっていたのかと。「難聴」という理由だけで。 難聴児を抱えた親は子がどの様な人生を歩むのか気をもみ、私の母の様に憔悴してしまう方が多いだろうか。 そんな人たちに向け、難聴児から育ってきた私自身が全く普通に生活していることを、このZENPEの場で記していければと考えている。 若かりし頃の母の写真は白黒である。父の愛車に寄り添ってあえてカメラから目線を外し微笑んでいる。 彼女に言ってあげたい。私は普通の人生を歩む。だからどうか気にしないで欲しい。そして、それはあなたのお陰だと。 私の場合、症状の進行は本当に緩やかです。ただ、目眩特有の眼球運動になっていると慶應義塾の診察で指摘されています。あまり自覚ないですが。 思い返せば、確かに夜中に気持ち悪くなり嘔吐したり、意味なくグルグルと地面が回っているのを感じたこともありました。和太鼓にハマっていた時期、締め太鼓の高い音を聞くと、ぐるっと頭の中が回転するような気味の悪い感覚がいつもありました。それでも、そういった身体の訴えを無知さから強引に無視し続け「原因不明!疲れているんだと」と咀嚼しておりました。 その間、緩やかに聴力は下がり続けていたのですが、そのことをあまり自覚しておらず、補聴器が調子悪くなってきたと捉えていました。経年劣化で補聴器はどんどん出力が弱るものだ、日によって補聴器が調子悪いなと、その様に思っていました。でも、あたりめ事件により突発難聴を経験してから危機感を抱くようになり、改めて自身の難聴を見直す様になりました。そして、補聴器の劣化だと思っていたものが、そうではなかったと知ったのは慶應義塾にお世話になってからです。天動説全盛の私の頭の中に地動説が提唱され、それは本当にショックを受けました。補聴器が不安定なのではなく、私の聴力が不安定なんだと。その時既に40代です。難聴のプロだと思っていたのに、自分の聴力が低下していることに全く気づいていなかったのですね。。恐ろしい。 そこから耳を労ることを真剣に考え始め、ストレスの向き合い方を勉強するようになりました。仕事に対する姿勢にもそれは表れているかも知れません。 そんな普通のおじさんですがZENPEの活動を支えることで、私の母のように苦悩を感じてしまう方が少しでも減ればと考えております。
ZENPE監事 竹原 綾子
監事 竹原 綾子 profile 国内某航空会社へ入社し、客室乗務員として5年間務め、結婚を機に愛知県に在住し3年後に息子を授かり、その6年後に娘も授かりました。 娘の中学受験と息子の大学受験が終わり、兼ねてから生花 草月流の師範を習得していたので、アーティフィシャルのフラワーアレンジメント教室 『StyleK』を立ち上げました。 そこで出していたランチが好評で、開催2年後にお料理教室も始めることになりました。 現在15年目に入りますが、昨年末息子の子供の誕生もあり、教室運営は少し縮小しています。 今後は、ZENPEの一員とにして、少しでも皆様とコミニケーションを取りながらお役に立てることが出来るよう活動していけたらと思っています。 message 出産は逆子の為帝王切開にて産まれた息子は、哺乳力が弱めで1時間かけてミルクを呑む赤ちゃんでした。そのため出生時の体重は2922gありましたが、7日後の退院時は2600gまで減ってしまいました。その後は体重計をレンタルし、息子の体重を増やすため、母乳とミルクを必死にあげていたように思います。1時間かけたミルクを噴水のように吐くことも多く、育てにくさはありましたが、欲しくてやっと授かった我が子が愛おしく授かってくれた命に感謝と可愛さで毎日が楽しくて仕方がありませんでした。 彼に何ができるか? やれる事全部してあげたいと思い、育児書、子育て論を幅広く熟読しました。首の座りも遅く反り返りも多かったので、4ヶ月の時は脳性麻痺の疑いがあると言われ、大学病院を受診したこともありました。 まだ何も分からない時から絵本の読み聞かせや手遊びをしていたせいか、1歳2ヶ月ではひらがなを習得し、オムツも取れていたので、知的障害はないと安堵したのを思い出します。それでも、視覚での反応に比べると明らかに聴覚での反応が鈍く、聞こえに不安を感じていました。 そんな中、幼稚園から帰宅した息子が聞こえに全く反応がない為慌てて病院へ行くと、前庭水管拡大症と診断されました。どうやら幼稚園での前転を数回したことが原因だったようです。大きなショックと不安が押し寄せましたが、それと同時に私には何ができるか、彼に何を働きかけられるかにフォーカスして子育てをしていこうと決意しました。 意気込んだものの、この病気に関しての情報があまりにも少なく、当時ホームページビルダーでホームページを立ち上げ、掲示板を貼り付け同じ病気を持つ保護者の方とコミニケーションを試みましたが、今ほどSNSなどが浸透していなかった為思うように情報を収集することは困難でした。 日々彼の聴力がほんの少しの事でも変動を繰り返し低下していく為、もどかしさに苛まれました。その度に私が落ち込む傍ら磊落な息子にどれだけ助けられたかわかりません。幼い頃からの働きのおかげか、聴力が衰えているからなのか、記憶力に長けていたように思います。 その甲斐あって国公立の医学部に現役で合格してくれた時に私の中で安堵感に包まれ少しだけ肩の荷がおりたと感じました。 この病気はMRIが導入されてからわかったこともあり、圧倒的に情報収集が難しくどのような経過を辿っていくか不安な中、毎日模索しながらの子育てでした。 子育てに一段落はしたものの、現在子育中のご家族の皆さまに少しでもお役に立てたらと言う思いで、Instagramなどで発信を始めたところ、ZENPEの代表、大島美和さんに出逢う事が出来ました。美和さんの抜群の行動力でNPOの立ち上げのお話を頂き、非力ではありますがこの障害を持ちながらも社会で活躍できる人になれると言う事を皆様に少しでもお伝え出来たらと言う思いで参加させて頂くことになりました。
ZENPE代表 大島 美和
代表 大島 美和 profile 幼い頃から物づくりをしながら過ごす。 大学卒業後、設計事務所に従事。若者に人気のファッションブランドの立ち上げから携わるなど、店舗デザインを多数手がける。 デザイナーとして活動する傍ら、独学で写真撮影にも没頭。ミュージシャンの友人からのご縁で、ライブ撮影をはじめる。 設計事務所を退職後、フリーのカメラマンに転身。大手レコード会社のライブ撮影やCDジャケット、ファッション誌の表紙など人物撮影をメインに活動。それと並行してアート活動にも邁進。 2010年海外進出フランスで祈りの手のひらの写真を使用した立体曼荼羅オブジェを展示。 2011年10月パリの現代芸術の中心施設、ポンビドゥー・センターで祈りの手のシリーズ写真を展示し、好評を得るなど各地で個展を精力的に開催。 その後、結婚し出産。 2022年生まれの娘が前庭水管拡大症と診断を受ける。当疾患の情報の少なさから生後半年の頃に患者家族会の設立を決意。 設立に向けた準備を地道に進め、現在に至る。 message 私は高齢出産で初産だったため、大学病院に入院しました。逆子だったことから帝王切開で出産しましたが、生後数日で娘の哺乳力が弱いと診断され、GCU(新生児特定集中治療室)に移されました。コロナ禍のピークで、家族とも面会出来ない中での孤独感と不安に苛まれた日々は、今でも忘れられません。 その後、新生児聴覚スクリーニング検査で片耳難聴が判明。さらに「前庭水管拡大症」という診断が下されました。幸せの絶頂だと想像していた産後が一転して悪い方向へと展開していき、大きな戸惑いを感じました。 初めて耳にする病名に「間違いであってほしい」と何度も願いましたが、次々と押し寄せる現実を前に、心の準備が追いつかず、産後の不安定な精神状態も重なって、人生で最も辛い時期に感じられました。それでも、診断に至る過程や医師の説明を通じて、少しずつ現実を受け止め、前を向いて頑張ろうという気持ちが芽生えました。 当時、周囲に難聴の方がいなかったため、難聴やこの疾患について十分に理解することが難しく、初めての子育てに対して大きな不安を感じていました。 病名で検索を試みても、医師向けの論文ばかりがヒットし、SNSでも情報がほとんど得られない状況でした。私と同じように情報がなくて困っている人が他にもいるだろうと考えるようになり、情報を広く届ける仕組みを作りたいと思い立ち、子供が生後半年の頃に患者家族会の設立を決意しました。 それから多くの方々の支援を受けながら準備を進めました。他の患者家族会の代表やNPOの方々から話を聞き、どうすれば患者家族の皆様にとって有益な会になるかを模索しながら、素人ながらホームページ制作にも取り組みました。 設立を決意してから約2年後、嬉しい出来事が起こりました。国立病院機構東京医療センターの松永達雄先生が代表顧問医師として協力してくださることになったのです。松永先生は、私が疾患について調べていた時に何度もお名前を目にした、尊敬する医師でした。 さらに、北里大学の藤岡正人先生、東邦大学の瀬戸由記子先生も顧問医師をお引き受けくださり、素晴らしい体制が整いました。松永先生の医療監修のもと、患者家族に有益で正確な情報を提供できるよう、さらに努力を続けます。 私たちは「新薬の国内承認」と「指定難病化」を2大目標に掲げ、皆さまの温かい支援と共に少しずつ前進し、疾患の認知度向上と患者家族が支え合える環境づくりに取り組んでいきます。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。